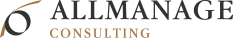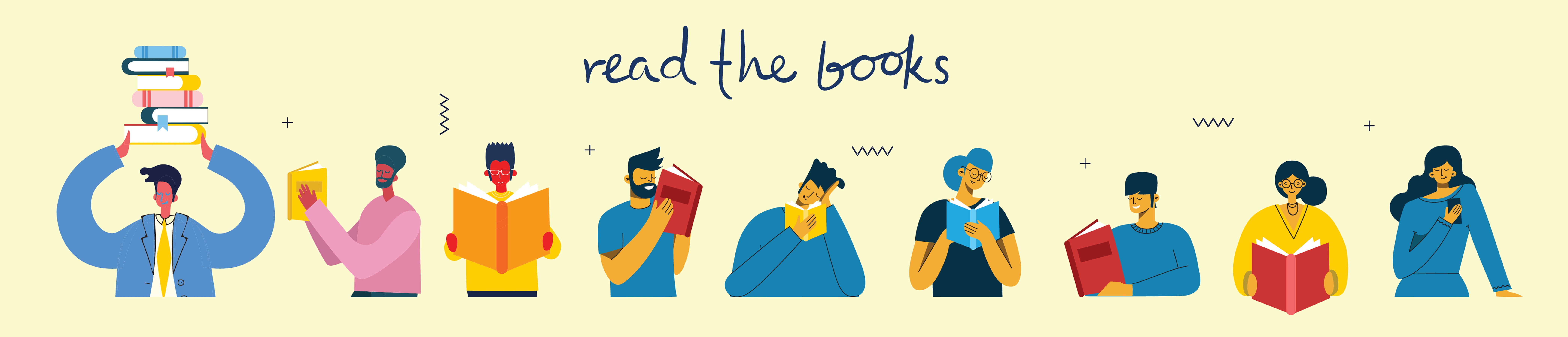
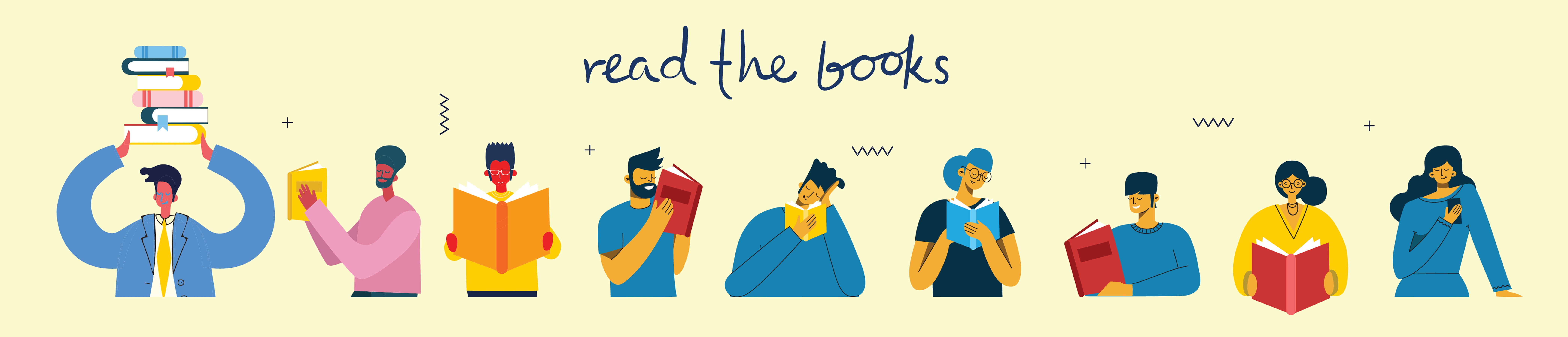
厚生労働省による医療機関へのサイバーセキュリティ推進施策とは
業種別動向

近年、医療機関がサイバー攻撃の標的になるケースが増えています。そこで厚生労働省は医療機関に対するサイバーセキュリティの強化を推進しています。本記事では、厚労省の推進事情と具体的な対策について解説します。
厚生労働省による医療機関へのサイバーセキュリティ推進施策とは
サイバー攻撃がもたらすリスクの深刻化
近年、サイバー攻撃は高度化・巧妙化しており、医療機関もその標的となりつつあります。医療機関がサイバー攻撃を受けた場合、個人情報の漏洩や医療サービスの停止など、深刻な事態に陥る可能性があります。
医療情報システムは、患者の個人情報や診療記録など、非常に重要な情報を取り扱っており、これらの情報が不正アクセスや改ざんによって流出してしまうと、患者や医療機関にとって深刻な被害をもたらします。
例えば、2017年には、アメリカの病院がランサムウェア攻撃を受け、患者の診療記録や個人情報が盗難され、病院のシステムが停止する事態が発生しました。この事件では、病院は多額の身代金を支払うことを余儀なくされ、患者の治療にも大きな支障をきたしました。
また、医療サービスの停止は、患者の生命や健康に直接的な影響を与える可能性があり、社会全体に大きな混乱を引き起こす可能性も懸念されます。
医療機関の現状と課題
現状、医療機関のセキュリティ対策は万全ではなく、改善が求められています。医療機関は、他の業種に比べてセキュリティ対策の遅れが目立っており、多くの医療機関がサイバー攻撃に対して十分な対策を講じていないのが現状です。
厚生労働省が2021年に行った調査によると、医療機関の約7割がサイバー攻撃対策として「セキュリティソフトの導入」や「職員へのセキュリティ教育」を実施しているものの、その効果については疑問視する声も上がっています。
その原因としては、医療機関の経営状況や人材不足、セキュリティ対策に関する知識不足などが挙げられます。医療機関は、限られた予算や人員の中で、診療業務を優先せざるを得ない状況であり、セキュリティ対策に十分なリソースを割くことが難しいケースも少なくありません。
また、医療従事者は、セキュリティ対策よりも診療業務に集中することが求められるため、セキュリティ対策に関する知識や意識が低い傾向にあります。
さらに、医療機関は、患者のプライバシー保護の観点から、情報公開に慎重になる傾向があり、セキュリティ対策に関する情報共有が不足しているケースも見られます。
厚労省の対応と推進施策
厚労省は、医療機関に対するサポートを強化し、サイバーセキュリティ対策の推進を行っています。厚労省は、医療機関のサイバーセキュリティ対策の重要性を認識し、様々な施策を展開しています。
具体的には、医療情報システムの安全管理ガイドラインの策定、セキュリティ対策に関する研修やセミナーの開催、医療機関向けの助成金の提供などを行っています。
また、厚労省は、医療機関と連携して、サイバー攻撃に対する備えを強化するための取り組みを進めています。
具体的なセキュリティ対策
医療情報システムの安全管理
医療情報システムの安全管理には、適切なアクセス制御、データの暗号化、定期的なセキュリティパッチの適用など、様々な対策が必要です。
厚労省は、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインを策定し、医療機関に対して安全なシステム運用を推奨しています。
このガイドラインでは、医療情報システムの安全管理に必要な対策を具体的に示しており、医療機関は、このガイドラインを参考に、自院のシステム環境を点検し、必要な対策を講じる必要があります。
研修とトレーニングの実施
医療従事者のセキュリティ意識向上のためには、定期的な研修やトレーニングが不可欠です。研修では、サイバー攻撃の手口や対策方法、情報セキュリティに関する法令などを学ぶことができます。
また、トレーニングでは、実際にセキュリティ対策ソフトの操作方法や情報漏洩時の対応手順などを学ぶことができます。
外部ベンダーとの協力
医療機関は、自社の専門知識だけでは対応できないセキュリティ対策も存在します。
そのため、システムベンダーなどの外部専門機関と連携し、適切なセキュリティ対策を導入することが重要です。
外部ベンダーは、最新のセキュリティ技術や脅威情報に関する知識を有しており、医療機関のセキュリティ対策を支援することができます。
サイバー攻撃を受けた場合の対応
迅速な連絡体制の確立
サイバー攻撃が発生した場合、迅速な対応が被害を最小限に抑えるために重要です。
そのため、医療機関は、サイバー攻撃発生時の連絡体制を事前に確立しておく必要があります。
連絡先は、警察、情報セキュリティ対策会社、厚労省など、関係機関を網羅しておくことが重要です。
事業継続計画(BCP)の策定
BCPは、災害や事故など、予期せぬ事態が発生した場合に、事業を継続するための計画です。
サイバー攻撃も、事業を停止させる可能性のある事態の一つです。
そのため、医療機関は、サイバー攻撃を想定したBCPを策定し、攻撃発生時の対応手順や事業再開までの手順などを明確にしておく必要があります。
情報漏洩時の対応手順
サイバー攻撃によって個人情報が漏洩した場合、迅速かつ適切な対応が求められます。
そのため、医療機関は、情報漏洩時の対応手順を事前に確立しておく必要があります。
対応手順には、情報漏洩の確認、被害状況の把握、関係機関への報告、情報漏洩の防止対策などが含まれます。
推進事例の紹介
成功事例から学ぶ
医療機関のサイバーセキュリティ対策の推進には、成功事例を参考に学ぶことが重要です。
厚労省は、セキュリティ対策に成功した医療機関の事例を公開しており、他の医療機関は、これらの事例を参考に、自院のセキュリティ対策を強化することができます。
厚労省の取り組み事例
厚労省は、医療機関のサイバーセキュリティ対策を強化するため、様々な取り組みを行っています。
例えば、医療情報システムの安全管理に関するガイドラインの改訂、セキュリティ対策に関する研修やセミナーの開催、医療機関向けの助成金の提供などです。
これらの取り組みを通じて、厚労省は、医療機関のセキュリティ対策のレベル向上を目指しています。
民間との連携強化
厚労省は、民間企業との連携を強化することで、医療機関のサイバーセキュリティ対策をより効果的に推進しています。
例えば、セキュリティ対策ソフトの開発会社やセキュリティ対策コンサルタント会社など、様々な民間企業と連携し、医療機関に最適なセキュリティ対策を提供しています。
まとめ
今後の課題と展望
医療機関のサイバーセキュリティ対策は、常に進化するサイバー攻撃に対応していく必要があります。
そのため、厚労省は、今後も最新の脅威情報や技術動向を把握し、医療機関に対して適切な対策を指導していく必要があります。
また、医療機関自身も、セキュリティ対策の重要性を認識し、積極的に取り組むことが重要です。
医療機関の役割
医療機関は、厚労省の指導を参考に、自院のセキュリティ対策を強化していく必要があります。
具体的には、医療情報システムの安全管理、職員向けのセキュリティ研修、外部ベンダーとの協力など、様々な取り組みが必要です。
厚労省との連携の重要性
厚労省と医療機関の連携がセキュリティ対策の鍵となります。厚労省は、医療機関のサイバーセキュリティ対策を支援するための様々な施策を展開しています。医療機関は、厚労省の施策を積極的に活用し、連携を強化することで、より効果的なセキュリティ対策を推進することができます。厚労省と医療機関が連携することで、医療機関のサイバーセキュリティ対策のレベル向上に貢献することができます。